2025年の夏、高速道路のすぐそばでクマがシカを襲う──そんな衝撃的なニュースを目にした。人の目と鼻の先で、野生の捕食が起きていた。
その瞬間、私はふと祖母との何気ない会話を思い出した。
子どもの頃、私は毎年の夏休みを、北海道の北部にある祖父母の家で過ごしていた。飛行機で稚内空港に降り立ち、さらに車で日本海側を1時間ほど走る。右手に利尻富士と青く広がる日本海、左手には果てしなく続く牧草地と山林。そんな一本道を、ただひたすら進んでいく。
車窓から見える深い森を眺めながら、その奥に潜む生き物たちを想像するのが、私の密かな楽しみだった。
祖母はその地で10人兄弟の長女として生まれた。病弱な母に代わり、幼い頃から家の手伝いや奉公に出て、遊ぶ暇などない子ども時代を過ごしたという。
祖母の父──つまり私の曽祖父は猟師だったのか、あるいは猟師を兼任していたのかは定かではない。ただ、山で仕留めた獲物が食卓に並ぶのは珍しくなかったそうだ。
祖母にとって、山はただの自然ではなかった。
生きるための場所であり、糧を得るための場。
そんな山を相手に暮らしてきた人の言葉には、静かだけれど揺るぎない重みがあった。
ある日、私は何気なく祖母に聞いたことがある。
「クマって、シカを食べるの?」と。
その時の会話の前後はもう覚えていない。けれど、祖母の返事だけはなぜか、ずっと心のどこかに残っていた。
「クマはね、普段は山の木の実とかを食べてるんだよ。よっぽどお腹がすいたときとか、冬眠から目覚めたばかりのときじゃないと、シカなんてわざわざ捕まえないのさ」
その記憶が、あのニュースを見た瞬間に、ふいに蘇った。
▶︎【北海道】高速道路でクマがシカを襲う瞬間(YouTube)
高速道路のすぐそばで、クマがシカを襲っている。
「よっぽどお腹がすいてたんじゃないか」──その感想は、ただの憶測ではなく、山で何かがおかしくなっているという“サイン”のように思えた。
かつては山の奥深くで静かに営まれていたはずの命のやりとりが、今は人のすぐ目の前で起きている。
しかも、獲物はシカ。
祖母が「よっぽどのとき」と語っていた行動が、現実となって目の前に現れた。
それは、クマが「よっぽど」空腹でなければ近づかないはずの人のそばにまで出てきて、
「よっぽど」でなければ狙わないシカを襲っている、ということだ。
例外に例外が重なる──それほどまでに、山で異変が起きているのではないか。
2025年、東北森林管理局はブナの実が「大凶作」であると発表し、クマの人里への出没が増えると警鐘を鳴らした。
▶︎【毎日新聞】ブナの実「大凶作」でクマ出没増か
さらに、猛暑の影響で虫の数も激減している。虫が少ないということは、それを食べるスズメバチや、それを狙うクマたちの食料も失われているということ。
加えて、前年に山の実りが豊作だったため、クマの出産数が増え、現在は多くの母グマが子育ての真っ最中。必死に食べ物を探していると考えられる。
自然が生活のすぐそばにあった人の言葉は、決して感傷的な懐古ではない。
それは、山の変化を肌で感じながら暮らしてきた人の“実感”だ。
その実感が、今の私にとって確かな指針となっている。
もちろん、祖母の時代とは気象条件も大きく変わっている。
私自身、30年前の北海道と今の北海道では、気候も山の様子もまるで違うことを実感している。
祖母はもう、あの頃のように山の話を語ってはくれない。
けれど、あのときの静かな声と、自然と共に暮らしていた人のまなざしは、今も私の中に生き続けている。
その記憶を道しるべに、私はこれからも山の声に、耳をすませていきたいと思う。
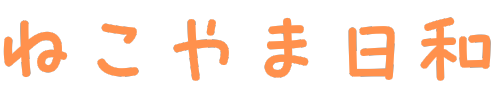

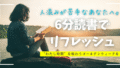
コメント